蓄積型熱中症とは?原因と今から実践できる対策
column
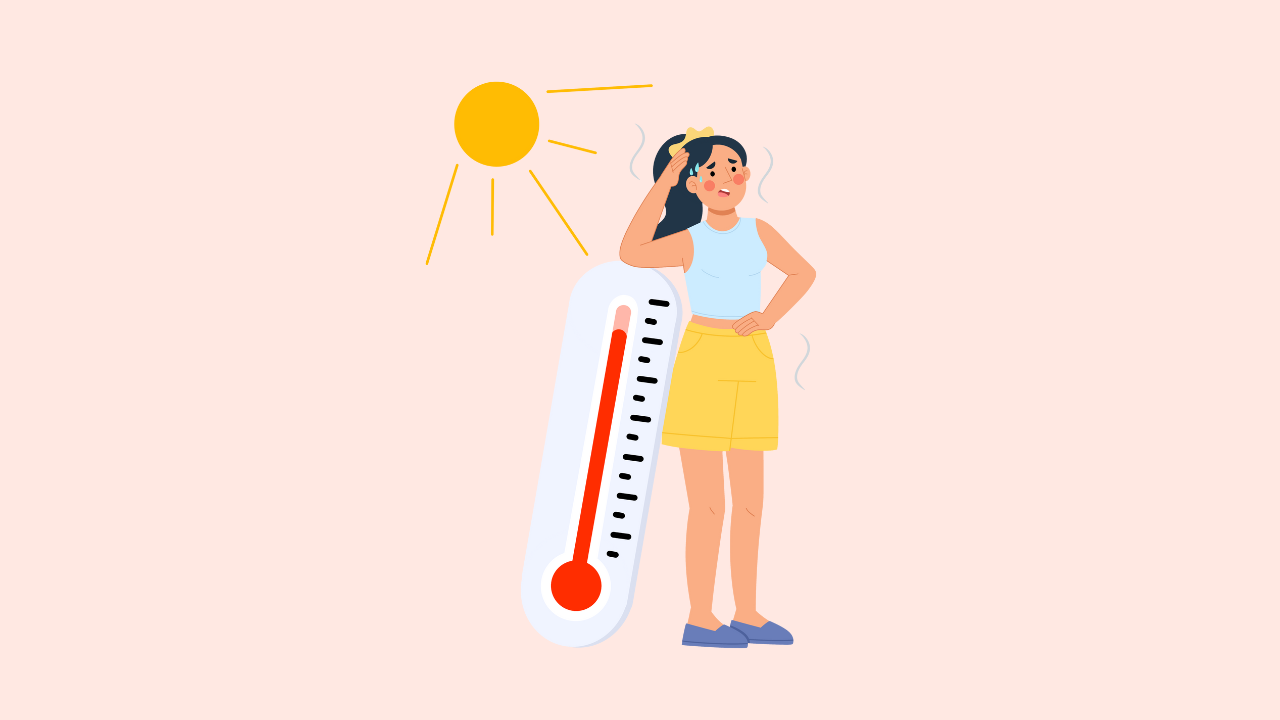
- コラム
近年、夏の猛暑だけでなく秋でも熱中症にかかる人が増えており、その中でも注目されているのが「蓄積型熱中症」です。
従来の熱中症は炎天下で突然発症するイメージが強いですが、蓄積型熱中症は知らないうちに体に疲労や熱がたまり、数日後に体調不良として現れるのが特徴です。
今回は、蓄積型熱中症の原因や症状、そして今日から実践できる予防対策を解説します。
蓄積型熱中症とは
「蓄積型熱中症」とは、暑い環境での生活や作業によって体に熱や疲労が少しずつ蓄積し、時間をかけて発症するタイプの熱中症です。
通常の熱中症が数時間のうちに急に発症するのに対し、蓄積型は数日間の疲労・睡眠不足・水分不足などが積み重なって体調不良を招くのが大きな違いです。
そのため、不調を起こしたときに蓄積型熱中症が原因だと気づく人も少なく、つい症状を放置してしまうということが懸念されます。
蓄積型熱中症の原因
蓄積型熱中症は簡潔にいうと「体が熱に適応できない状態」が続くことで起こります。
蓄積型熱中症を引き起こす主な原因としては、以下の通りです。
1. 睡眠不足
夜間の室温が高いと深い睡眠が取れず、体の回復が妨げられます。その結果、自律神経の働きが乱れ、体温調節がうまくいかなくなります。
2. 水分不足・ミネラル不足
発汗で失われた水分や塩分を補給できていないと、体温を下げるための汗の質が悪化し、熱がこもりやすくなります。
3. 疲労の蓄積
連日の仕事や運動で体に疲労が蓄積すると、体温調節機能が低下しやすくなります。特に屋外作業やスポーツを行う人は要注意です。
4. 高温多湿の環境
エアコンを使わずに過ごす、風通しの悪い部屋で寝るなど、高温多湿の環境が続くと、体の熱が放出されず蓄積していきます。
蓄積型熱中症の症状
蓄積型熱中症の発症初期は「ちょっと疲れているだけ」と思いやすいため、つい見逃されがちです。
その後、下記のような症状が主に起こりやすくなるとされています。
- 体のだるさ、疲労感
- 食欲不振
- 軽い頭痛やめまい
- 立ちくらみ
- 微熱、体の熱っぽさ
- 集中力の低下
ここからさらに重症化すると、吐き気や意識障害、けいれんといった危険な症状に至ることもあり、命に関わる危険な状態に陥る恐れもあります。
「数日間だるさが続く」「食欲が落ちている」といった変化は、単なる夏バテではなく蓄積型熱中症のサインかもしれませんので、軽くみるのは危険です。
今から実践できる対策
蓄積型熱中症は「いかに体に熱をためないか」がポイントです。今日から取り入れられる予防法をご紹介します。
1. 睡眠環境を整える
- エアコンや扇風機を活用し、室温は25〜28℃程度に保つ
- 吸湿性・通気性の良い寝具を選ぶ
- 寝る前にぬるめのシャワーで体温を下げる
質の良い睡眠は、翌日の体温調節機能を維持するために欠かせません。
2. 水分・塩分補給をこまめに行う
- のどが渇く前に水分補給する
- 大量に汗をかく場合はスポーツドリンクや経口補水液を利用
- カフェインやアルコールは利尿作用があるため、摂りすぎに注意
目安として、1日あたり1.2〜1.5リットルの水分を数回に分けて摂取するのが理想です。
3. 食事で栄養をしっかり摂る
- ビタミンB群:疲労回復に役立つ(豚肉、納豆など)
- ビタミンC:ストレス対策(果物、野菜)
- 塩分:汗で失われやすいため、味噌汁や梅干しで補給
偏った食事は熱中症リスクを高めるため、バランスの取れた食生活を心がけましょう。
4. 日常生活での工夫
- 日中の外出は日傘や帽子を活用
- 吸湿速乾性のある服を着る
- 帰宅後はシャワーや冷却グッズで体を冷やす
- クーラーを我慢せず、快適な室温で過ごす
蓄積型熱中症は、放置せず適切な予防・治療を
蓄積型熱中症は「毎日の小さな油断の積み重ね」で発症します。逆に言えば、日々の生活習慣を少しずつ整えることで予防が可能です。
特に高齢者や子ども、持病のある方は体温調節が苦手なため、家族や周囲の人が注意を払うことも大切です。
「最近疲れが取れない」「食欲が落ちている」と感じたら、無理をせず休養を取りましょう。そして症状が強い場合や長引く場合は、早めに医療機関を受診することが重要です。
連日の猛暑で不調を抱えている方や、もしかしたら蓄積型熱中症かも?とお悩みの方は、お気軽にご相談ください。





